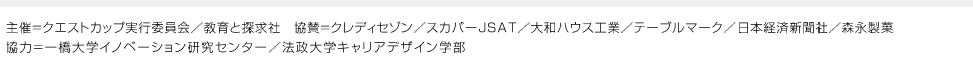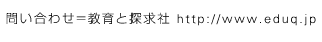人が集い、歓び、つながる 100年続くまちづくり計画を提案せよ!

当日の審査を振り返って
今年見事、大和ハウス賞に輝いたのは、常翔学園高等学校「THE BEST HOUCHU」チーム。
プレゼンの冒頭、スライドに大きく映し出される「夢」の一文字。
「夜寝てみるのも夢、過去の思い出も夢・・・
しかし、われわれにとって重要な夢は将来の夢でなければならないのです」
と大和ハウス創業者石橋信夫氏の言葉をゆったり語り、
「これから私たちの100年続く夢の話をします」と切り出した。
まるで創業者が夢の続きを語り出したかのような雰囲気に会場は包まれる。
提案のコンセプトは「Earth in Earth」、地球の中に地球をつくろうというもの。
世界中の人々が一つのまちに住み、文化や伝統、誇りをお互いに共有、理解し合うことで、
世界平和のきっかけをつくるという斬新なものであった。
発表を最前列で聞いていた審査委員は思わず感涙。
ミッションに対して創業者の想いというところまで掘り下げて、
そこから立ち上げたこの作品は「探究力」の点で抜きんでていた。

審査委員特別賞に輝いたのは、三重県立名張高等学校「チームバチスタ」。
プレゼンの派手さはないが、一言一言に重みを感じる内容であった。
「今から100年後に新建材を自然に戻すことができるのか?」
と根元的な疑問を投げかけ、審査委員を目の前に、
大和ハウスがこれまで推し進めてきた「建築の工業化」を真っ向から否定してみせた。
ミッションにある「日本の未来をここからつくる」ためには、
現状を一度壊してそこから再度立ち上げる必要がある。
このことの重要性にハッと気付かされた審査委員たちから
「特別賞は、名張に」という声が自然にあがった。
惜しくも受賞を逃したが、圧倒的な調査力を感じさせてくれたのは
埼玉県立新座総合技術高等学校「Cha!!enger」チーム。
100年続くまちの具体的な場所として埼玉県飯能市を想定し、
実際に飯能市役所へ乗り込んでの聞き込みを行った。
その上で、自分たちの思い描いていることが行政の施策では実現不可能だと知るやいなや、
「だったら、自分たちでやってしまえばいい」という切り替えの良さも見事だった。

明治大学付属明治高等学校「ダイワマンY」チームの作品は独創性が際立っていた。
新エネルギー、バイオテクノロジー、ロボット技術、コンピューター技術を駆使した
宇宙産業都市建設という壮大なスケールの提案であった。
宇宙エレベーターの開発など、実際に具体的な取り組みが
なされようとしているという情報も集め、絵空事ではない現実感のある提案であった。
また、「心のつながり」や「絆」にしっかりと焦点をあてたチームもあった。
鴎友学園女子高等学校「田イワハウチュ」チームは、「PEACE計画」と称して、
地域の中で世代を超えるつながりを実現するための企画を提案した。
特徴的だったのは、STと名付けた太陽光エネルギーで動く電子掲示板を使って、
まちの中での情報交換を効果的に行うというもの。
震災後、避難所の掲示板で安否確認をしていたことから発想したというアイディアだ。

クラーク記念国際高等学校横浜青葉キャンパス「ここにまちをつくろう」チームの提案は
実現性も高く、素晴らしいものだった。
血の通った人々のつながりや顔の見えるコミュニケーションを大事にしながら、
自分たちのまちは自分たちで何世代も守っていくというコンセプト。
つながりをうながす仕組みとして“絆”ポイントを貯めて、
“絆”サポートを受けられるという内容は公益性も高く、評価された。
日本が現在抱える社会的問題に鋭く切り込んだのは、
実践女子学園高等学校「大和マウチュポポポポーン」チーム。
舞台の袖で全員円陣を作って気持ちを一つにしてからプレゼンをスタート。
表現力では群を抜いていた。
提案内容は、日本で一番「自殺」の多い県、秋田に注目し、
秋田の名産品である「杉」を使って世代を超えたコミュニケーションを実現し、
地域のつながりを再生しようというものであった。

全体的な特徴としては、ミッションの中にある「集い、歓び、つながる」ための軸足を
「文化・伝統・家族」という「目には見えないけれど、
しっかりそこに存在するもの」にとらえる作品が多く見られた。
何かを外から持ってきて新しいまちを創るという発想ではなく、
その地域、その土地、そこに住むひとの素晴らしさに今一度焦点をあて、
そこを基軸に発想していくというものであった。
「日本の未来をここからつくる」。
まさに、その担い手となる若い人が大和ハウスからのミッションに正面からぶつかって、
自分たちなりの探求の道のりで
「自分たちの中にあるものから新しい発想が生まれていく感覚」に
気づいてくれたのではないだろうか。
どの作品にも、そのチームならではのぬくもりを感じることができた、
今年のファーストステージであった。